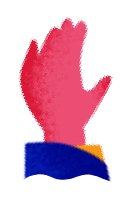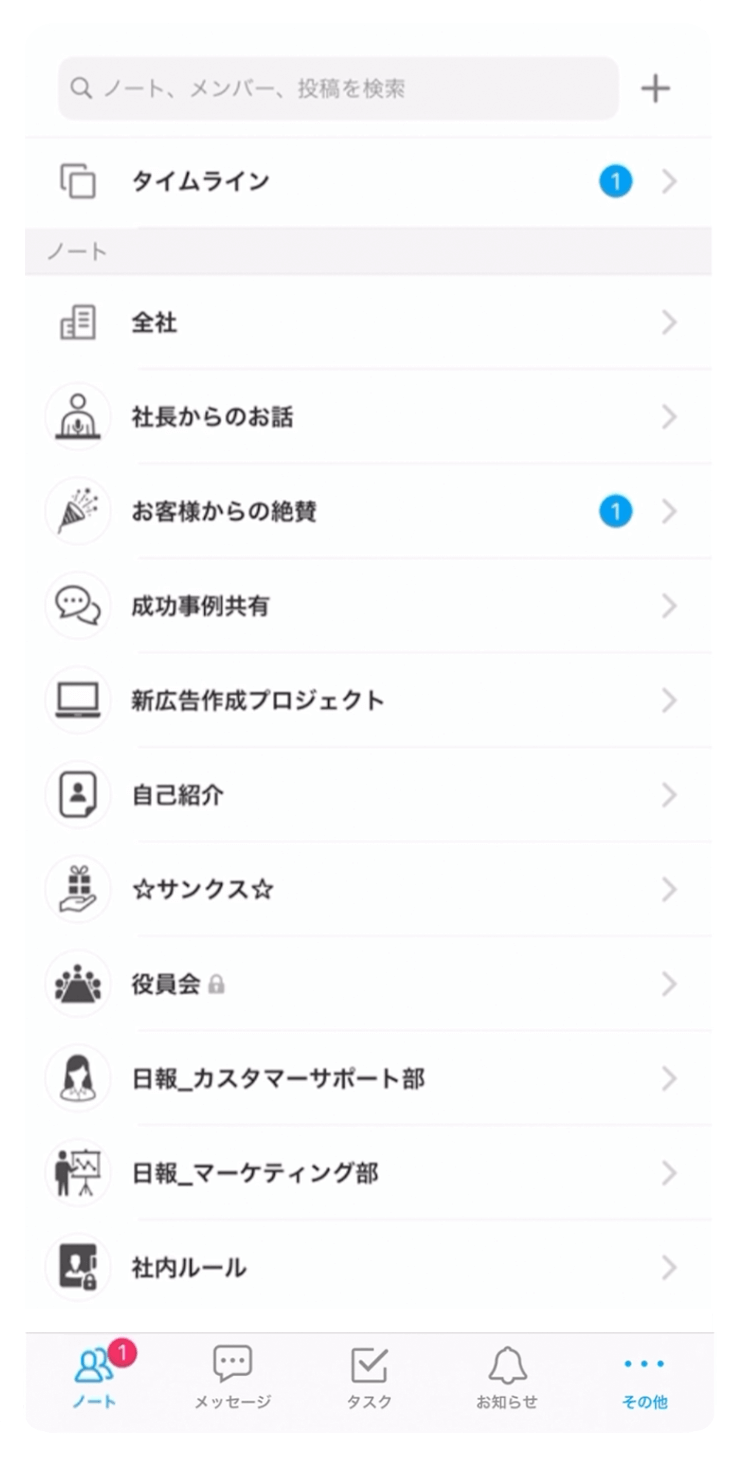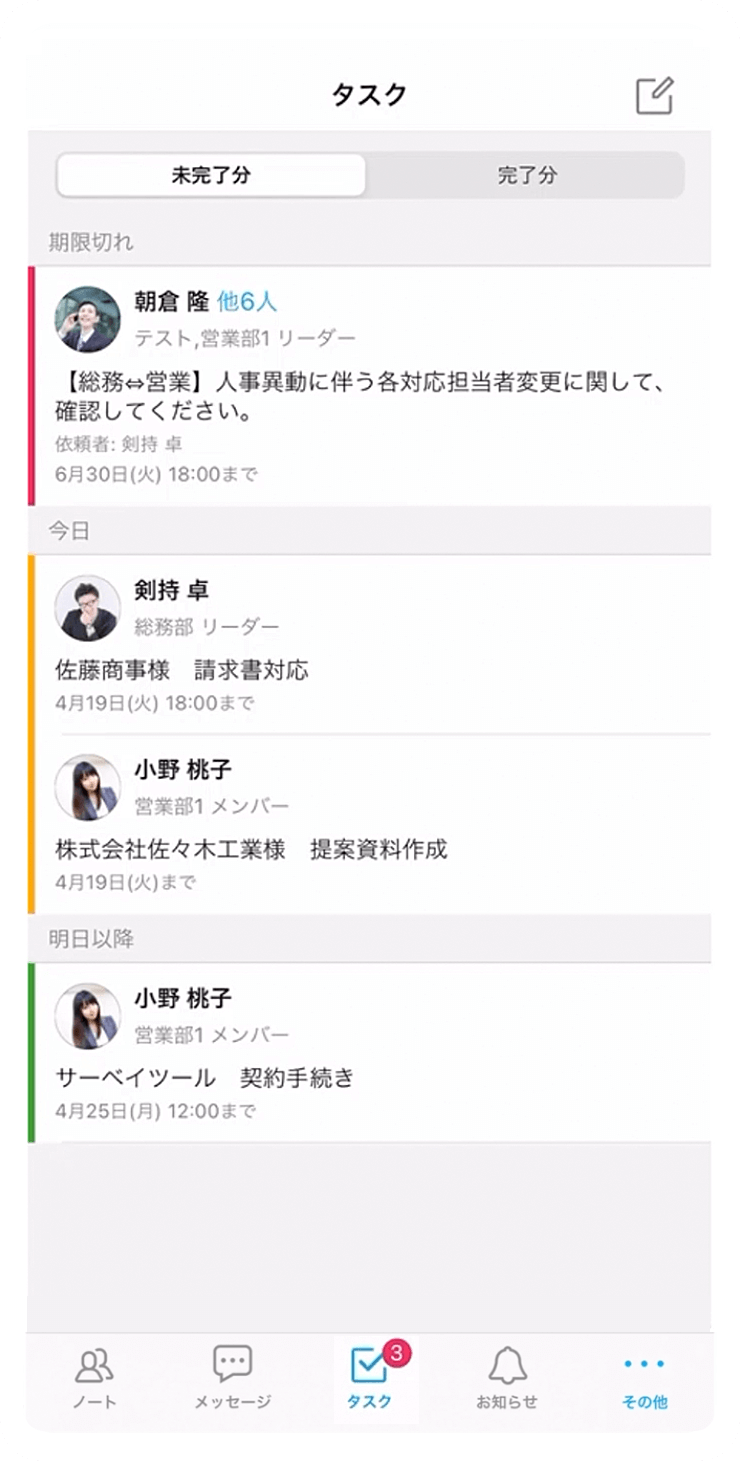マネージャークラス以上必見!「人材育成」の3つの成功ポイントとは?
「社会変化に人材育成が追いついていない」
「社員の成長意欲に応えられていないのではないか」
「グローバルに活躍できる人材が不足している」
激しい市場競争の中、どの企業にも人材に関する悩みがあるのではないでしょうか。人材育成は、企業の生き残りに関わる重要な施策です。自社に必要な人材を将来にわたり育てられるかどうかが、企業の存続を決めるといっても過言ではありません。本記事では、人材育成の理解を深め、成功へと導くポイントを解説します。
本記事のポイント
- 人材育成の意味を理解する
- 人材育成を成功させるためのフレームワークを知る
- 人材育成の具体的な手法を知る
人材育成が思うような成果を上げていないと感じているのであれば、基本から見直してみる必要があります。理解を深めるために、ぜひ本記事を参考にしてください。
人材育成とは?意味・目的について
企業における人材育成とは、「会社の経営戦略の実現に貢献できる人材へ成長させる」という意味があります。社員は、企業にとって最も重要な人的資産です。個々の社員の能力を高められれば、企業の力も強化できます。
これまでも企業は社員教育を行って成長を促してきました。現代において、過去の時代以上に人材育成が重要視されている理由は、企業を取り巻く社会・経済の大きな変化が背景にあるからです。
市場は、国内から高成長が期待される世界競争へと移行しています。一方、国内では人口構造の成熟化により、生産年齢人口が減少していく見込みです。グローバル人材やIT人材の不足はこの先もさけられないと予測されます。限られた人材リソースの中で、事業の質を高めていくには、人材育成が喫緊の課題となっているのです。
人材育成では、自社の戦力となるだけでなく、社員個人が「高い人間力」をもつことが重要視されます。人材育成を通じて、企業理念に貢献する社員に育てるためには、社員の目標と企業が掲げる目標が同じ方向を向いていなければなりません。
人材育成施策の計画
人材育成を実施していくためにも、「どのような施策を行うべきか」しっかりと検討しましょう。「あるべき姿」と「現状」のギャップを明確にしながら、「どうすればその差異を埋められるか」考察します。ここでは、考え方の流れを確認していきましょう。
①自社の課題を発見する
「戦略の課題」「組織の課題」「人材育成上の課題」に3分類して、整理するとわかりやすくなります。各課題についての現状を細かく把握し、分析を行いましょう。誰がどこでどのような業務についているのか、生産性の高低についても明確化するようにします。
②自社の戦略や目指す方向性を確認する
上記で出た各課題について、解決の必要性の有無や優先度を決めていきましょう。例えば、戦略が想定通りの結果を出せない理由が、「人材不足なのか」「組織的な問題なのか」によって、取りかかる順番が変わります。さらに、事業目標に対して「戦略が誤っていないか」「効率的か」を見直す方向性の確認も重要です。
③課題に合致する解決方法を検討する
最優先課題から順に、どのように解決するかアプローチを考えます。具体的な施策や、手法、人員配置、スケジュールなど細部にわたって内容を詰めていき、即時取り組んでいきましょう。
人材育成で活用すべきフレームワーク
人材育成施策を考える際には、フレームワークを活用すると進めやすくなります。一般的に、人材育成で有効とされる主なフレームワークを4つ紹介します。
ギャップ分析
「理想=あるべき姿」と現実の差異(ギャップ)を課題とし、理想を現実にするために何が欠けているのか、必要とされるものを分析する手法です。現状で不足しているものを考察すれば、それを補うための方法を見つけられます。
例えば、「判断力に乏しい」と分析された場合は、さまざまな現場を数多く体験させつつ裁量と責任を与えながら、トレーニングするのも方法の一つです。ギャップ分析の特徴として、現状の原因となる要因ではなく、理想とのギャップとなる「課題」に注目していきます。
コルブの経験学習モデル
経験学習とは、自らの経験から学ぶ方法です。経験学習モデルは、デイビット・コルブが提唱したフレームワークで、経験から学び得たものを活かしていくためのプロセスを理論化しています。経験学習モデルでは、以下の4つのプロセスを追求していきましょう。
- 経験
- 内省
- 概念化
- 実践
経験しただけで終わらせてはいけません。知識として蓄え、次回に実践していけば、成長を促すことができます。人材育成では、OJTとOff-JTをつなぐ考え方として活用されます。
7:2:1モデル
7:2:1モデルとは、人の成長を促すのは「経験7割」「人間関係2割」「研修1割」という考え方です。アメリカの研究機関による研究で明らかにされ、実際の仕事経験が最も成長に寄与するとされています。
座額は、人材育成でもある程度必要です。しかし、現場重視のほうがより一層成長を促進できるでしょう。人材育成に求められるのは、経験値やアドバイス、学習の適切な配分バランスです。
人材育成手法を決める
人材育成には、多くの手法があります。自社に合う手法を採用するには、それぞれのメリット・デメリットを理解しておきましょう。
①OJT(現場研修)
OJTとは、「On the Job Training」の略称です。実務を実践しながら、現場で業務知識を習得していきます。新人研修では、最も多く活用されている手法の一つです。
・メリット
業務の現場で実際の場面に合わせ、必要となる知識やスキルを身につけていくことができるため、実務能力を学ぶのに有効です。状況や相手に合わせながら、指導の仕方を調整できます。
・デメリット
1対1となるため、やや非効率で人件費から見ると高コストになる傾向があります。また、教える側のスキルにより、育成効果が左右される点もデメリットです。実際の業務と研修が同時進行するため、現場への負担がかかります。
②内部講師による集合研修
自社の社員を講師役にして、多人数への研修を実施する方法です。
・メリット
実務に即した専門スキルが習得でき、社員が培ったノウハウを伝えられます。多人数に対して一度に教育できるため、効率的です。
・デメリット
講師役の選定が難航する可能性があり、養成にも時間がかかります。実務から離れた座学となりやすいため、受講者により効果にばらつきが生じるかもしれません。
③外部講師による集合研修
専門職の講師を招き、対象者を一同に集めて行う研修方法です。
・メリット
各分野のエキスパートから学べ、社外のスタンダードな知識を習得できます。一度に多人数を対象とするため、効率的です。
・デメリット
外部講師の招へいコストが必要です。実務と離れた学習となるため、知識の実践化が難しい場合があります。対象者全員を1ヵ所に集めなければいけないため、研修管理者の負担が大きくなる点はデメリットです。
④ミニ集合研修(部内・課内研修)
ある程度の人数をグループ化し、社員が講師となって研修を行う方法です。
・メリット
少人数のため、場所選びが柔軟で実施しやすいのがメリットです。グループの属性に合わせて、教える内容を変えられます。
・デメリット
講師役の社員が多くなるため、業務を圧迫する恐れがあります。グループごとに研修内容が異なる場合には、テキストの標準化が難しくなるでしょう。また、グループに分けて実施するため、受講管理が複雑化する点もデメリットです。
⑤公開講座(外部講師)
外部事業者が開催する公開講座に、対象者を参加させる方法です。
・メリット
専門性の高い講師から、業界のスタンダードな知識を学べます。また、自社の企業規模にかかわらず、質の高い研修が実施できます。外部事業者が管理を行うため、自社の研修管理者の負担も軽減できるでしょう。
・デメリット
対象者全員分の受講費用がかかります。遠方の場合には、宿泊費用も考慮しなければなりません。外部がセットした講座内容となるため、自社向きのカスタマイズが難しいかもしれません。また、講座の日程が固定されており、自社の都合に合わせにくい点もあります。
⑥自己啓発(通信教育)
業務内容に合った通信教育を活用する方法です。
・メリット
時間の拘束がないため、自由に学習を促すことができます。学びたいものを、選んで学習したい対象者のニーズに合わせられることはメリットです。
・デメリット
自主性を重んじる方法のため、対象者の学習意欲により効果にばらつきが出やすくなります。実務への有用性を確認するのが難しいかもしれません。
⑦eラーニング
eラーニングシステムを活用し、オンラインで学習する方法です。
・メリット
時間や場所にとらわれず、空いた時間で学習可能です。研修会の開催と比べて、コストを軽減できる可能性があります。システム側が受講管理を行うため、担当者の負担が少ない点もメリットです。多くのシステムでは、単元テストやまとめテストなどにより、知識習得の確認ができる機能が搭載されています。
・デメリット
学習管理を個人に任せることが多いため、最後までしっかりと学習を完了できない可能性があります。画面による学習のため、実務に適用できない可能性も出てくるでしょう。自社の業務に合わせて学習内容をカスタマイズした場合には、コストが高額化します。
人材育成を成功させるための3つのポイント
人材育成の施策を単に実施するだけでは、意味がありません。各従業員が主体性をもち、自らが学ぶ姿勢が必要です。そのためには、人材育成担当者の対象者に対する的確な指導が求められます。人材育成を成功させるには、以下のような3つのポイントに留意していきましょう。
人材育成の目的を明確化する
人材育成の実施によって、どのような人材を得たいのかを明確にしていきましょう。現場の即戦力やグローバル人材、将来の幹部候補では、人材育成の手法が異なります。
社員の自発性を引き出す環境作り
社員の成長は、周囲からの圧力だけでかなうものではありません。自身がキャリアプランや、キャリアパスをしっかりと描いていけるよう、自発性を引き出すためのサポートをしていきます。
実践機会を設ける
フレームワークの章でも見てきたように、実務経験こそが成長のカギとなります。知識だけを詰め込む人材育成に偏ると、社員の成長が促進されません。知識の習得後には、関連業務による実践の機会を与え、スキルが身につくようなフォローをしていきましょう。
まとめ
人材育成の成功・不成功は、企業運営の安定性に大きな影響を与えかねません。形式ばかりの人材育成とならないよう、常に効果を測りながら適切な施策の方向性を探っていきましょう。社員の成長は、企業の成長と重なります。強い企業を作り上げていくには、正しい人材育成が不可欠です。
本記事で紹介したフレームワークや手法を検討し、自社なりの人材育成法を確立していきましょう。