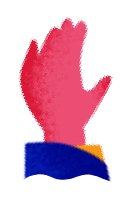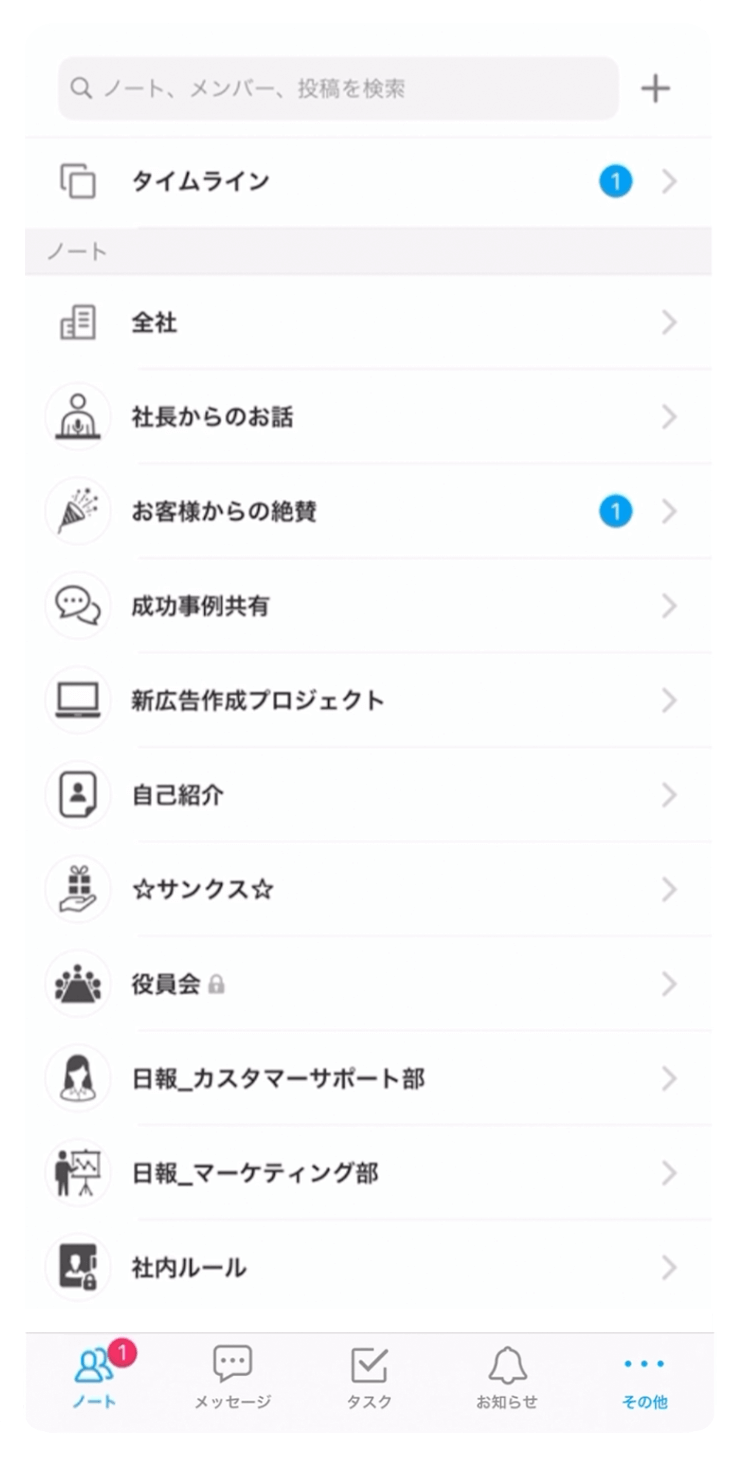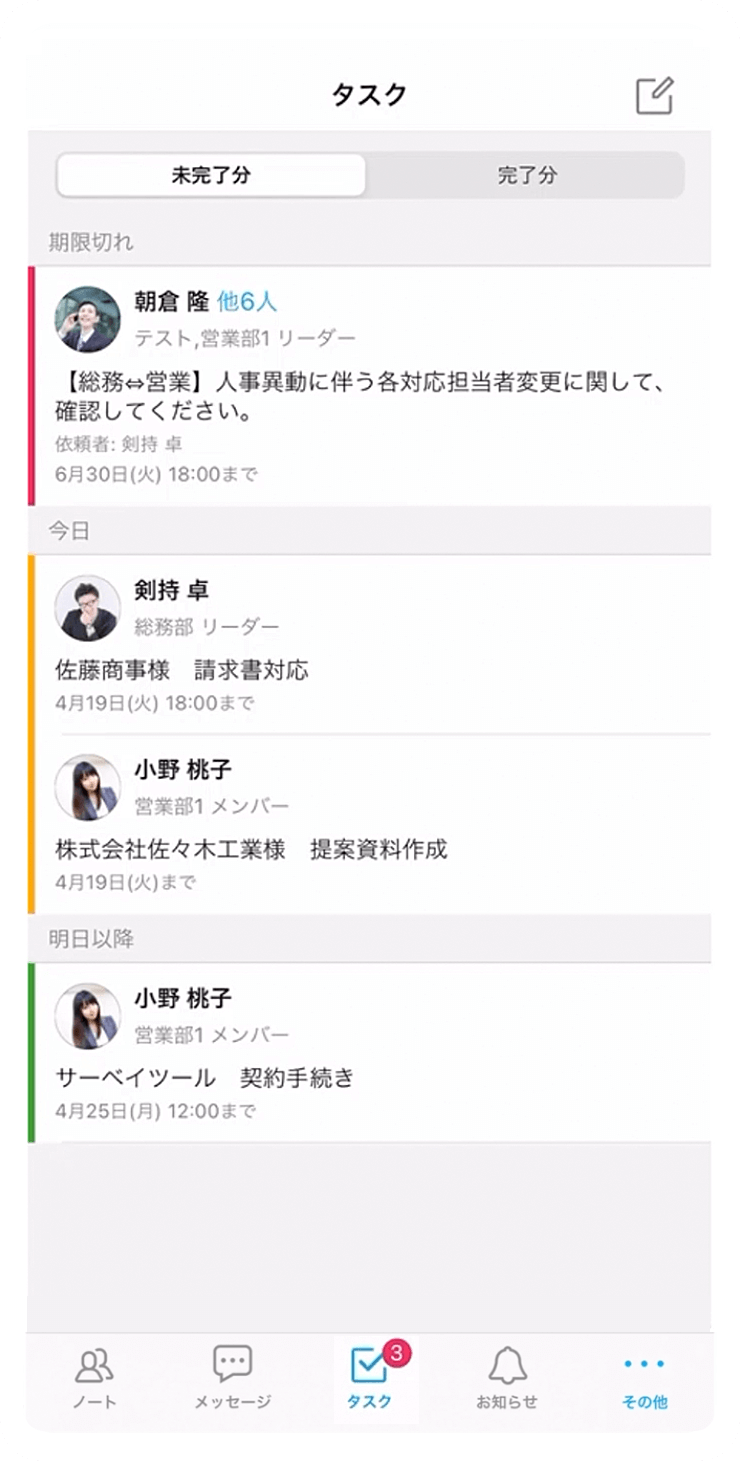クリティカルシンキングとは? 4つのステップとメリットを解説
ビジネスパーソンが注目している思考法はさまざまですが、今注目されているのがクリティカルシンキングです。日本語では「批判的思考」と表現され、批判するのではなく、前提を疑うことによって本質を見つける思考法のことを言います。
この記事では、クリティカルシンキングとロジカルシンキングの違い、基本的な姿勢、実践するための4つのステップ、メリットまで詳しく解説します。
クリティカルシンキングとは?
クリティカルシンキングとは、直訳すると批判的思考と表現される思考法です。「批判」という言葉から、ある事柄を否定的に思考する、欠点を追求する、粗探しをするなどと捉えられやすいですが、そうではありません。
デジタル大辞泉によると、「物事や情報を無批判に受け入れるのではなく、多様な角度から検討し、論理的・客観的に理解すること。批判的思考法。」と定義されています。
物事や情報に対してそのまま受け入れるのではなく、様々な角度から検討・理解するというのがクリティカルシンキングです。例えば、「近頃顧客からのクレームが増えている」という主張があったとして、そのまま受け取ると「クレームが多いから担当者の対応を見直そう」となるでしょう。
クリティカルシンキングは、どのようなクレームか、どのくらいの頻度か、過去と比べるとどうかなど、多角的に事柄を検討します。そうすると、担当者の対応ではなく商品・サービスに改善点が見つかったり、過去と比べるとそれほど件数が多くなかったりするなど、本質が見えてくるでしょう。このように、情報や主張を精査し、背景や本当の課題を見つけるために、クリティカルシンキングは重要な思考法です。
クリティカルシンキングとロジカルシンキングの違い
クリティカルシンキングと並んでポピュラーな思考法に、ロジカルシンキングがあります。類似するビジネス用語であるため、しばしば混同して理解しがちです。
クリティカルシンキングとロジカルシンキングの違いは、物事に対する考え方に違いがあります。
違いをわかりやすく理解するために、同じ事柄を設定しましょう。
- 広告Aに25万円、広告Bに25万円の費用がかかった
- 広告Aからの応募が70人、広告Bからの応募が30人だった
クリティカルシンキングは前提を疑うのがポイントで、そもそも50万円の広告費は妥当か、100人の応募は十分か、広告を出した求人媒体は適切だったか、広告以外の方法ではどうだったのかなどを考えます。
一方、ロジカルシンキングは、ある事柄の要素を細かく分けて思考し、筋道を立てて結果を導く思考法です。そのため、上記の事柄に対しては、同じ費用をかけた広告Aと広告Bを比べると、広告Aからの応募が多いことから、広告Aに50万円の費用をかけるべきという答えになります。
クリティカルシンキングの場合は、議論の結果、求人媒体や広告を変えたり、異なる方法でアプローチしたりするなど、手法自体が変更される可能性があります。一方、ロジカルシンキングでは、同じ手法の中でより適切な運用に改善することになるでしょう。
相反する思考法と理解しがちですが、考え方の違いから結果も異なるため、まったく違う思考法と言えます。
クリティカルシンキングはなぜ必要なのか?
クリティカルシンキングは、スピード感の増したビジネス環境に必要な思考法です。顧客のニーズは目まぐるしく変化し、新しい技術が日々登場しています。今日は需要の高いものでも、明日は他のものがとってかわっているかもしれません。
そのようなビジネス環境において、目に見える結果や情報だけで状況を読み取っていると、社会や競合他社に取り残される可能性があります。クリティカルシンキングによって、そもそもやり方が合っているのかなど、これまでとは違った角度で深く考察する必要が出てきたのです。
クリティカルシンキングの基本姿勢
クリティカルシンキングを実践するためには、思考することに対する姿勢が重要です。基本姿勢を意識することによって、スムーズに実践できます。
ここでは、意識したい5つの基本姿勢をチェックしていきましょう。
- 前提を疑う
- 目的を常に意識する
- 常に問い続ける
- 思考の癖があることを理解する
- 正しい情報を収集する
前提を疑う
クリティカルシンキングでまず大切になるのが、前提を疑う姿勢です。曖昧な言葉や抽象的な言葉に注目し、具体的にどうなのかを問うことによって思考が鍛えられていきます。
例えば、「繁忙期には、現在の人員では上手くいきません」という主張があったときに、繁忙期とは具体的にどのくらい忙しいのか、「上手くいきません」とは具体的にどのような状態かなどを考えましょう。
疑った前提に対して、具体的な内容を調べたり、根拠を考えたりすることによって、よりクリティカルシンキングの質が高まっていきます。
目的を常に意識する
クリティカルシンキングを実践するときは、何のために考えるのかという目的を常に意識しましょう。ただ考えるのではなく、目的を達成するために考えるのがクリティカルシンキングです。
まず目的を細部まで設定し、それに向かって思考を続けましょう。そうすることによって、ただの批判になってしまったり、無駄な議論をしたりすることを防げます。
常に問い続ける
クリティカルシンキングでは、常に問い続ける姿勢が重要です。すぐに答えが出たからといって問うことをやめてしまうと、そこで思考は止まってしまいます。
問い続け、考え抜くことがクリティカルシンキングをものにする近道です。MECEという用語があり、「もれなくだぶりなく」という意味があります。ある事柄について、前提や言葉の意味などを細かく考察し、MECEの状態になるまで考え続けるトレーニングをしましょう。
思考の癖があることを理解する
人それぞれ性格や価値観が異なり、思考にも癖があります。思考の偏りを理解していないと、どのような事柄でも似た答えを導いてしまうでしょう。
そのため、自分がどのように考えることが多いかを理解し、思考の幅を広げるトレーニングが必要です。ある事柄に対して、答えの質を問わず、様々な角度から自問することによって、癖から脱却した思考ができるようになります。
正しい情報を収集する
クリティカルシンキングのためには、知識や情報がなくてはいけません。引き出しがないと疑うことが難しく、そのまま受け入れてしまいがちであるからです。
知識や情報はただ知っているのではなく、思考や仕事に使えるものでなくてはいけません。読書や動画コンテンツなどで学び、他の人と意見を交流したり、フィードバックをもらったりすることが大切です。
クリティカルシンキングの4つのステップ
クリティカルシンキングは、4つのステップに分かれています。それぞれで重要なポイントを押さえて、クリティカルシンキングを実践しましょう。
- 【ステップ1】思考する目的を決める
- 【ステップ2】現状を分析する
- 【ステップ3】課題を発見する
- 【ステップ4】解決に向けたアクションを検討する
【ステップ1】思考する目的を決める
クリティカルシンキングを始める前に、思考する目的・ゴールを決めましょう。思考の結果、何をどのくらいのレベルで求めるのか、いつまでに達成するのかを明確に決めることが大切です。
このステップで目的が曖昧になると、クリティカルシンキングの効果が薄くなってしまいます。目標設定から明確に行うことが最終的な結果を決定づけるともいえるでしょう。
【ステップ2】現状を分析する
次に、目的に対して現状を分析します。ある状況に対して、現在がどうなのかを考えることはもちろん、調査も行い細部まで把握することがポイントです。
現状分析を丁寧に行えば行うほど、課題の発見や効果的な問いをしやすくなります。
【ステップ3】課題を発見する
現状分析の次は、課題を発見するステップに進みます。ここでは、目的に対して現状はどのくらい開きがあるのか、どのような部分が不足しているのかを考えましょう。
多角的に思考する必要があるので、一人ではなく、複数のメンバーで議論する方が効果的です。思考の癖を補いながら、クリティカルシンキングを進めましょう。
【ステップ4】解決に向けたアクションを検討する
発見した課題を踏まえて、解決に向けたアクションを検討しましょう。アクションを決定する際は、誰が・何を・いつまでに・どこで・どのようになどを具体的に決めることが大切です。
アクションを実行した後は、それで満足するのではなく、結果の分析と課題を見つめ続けましょう。クリティカルシンキングを継続することで、課題解決を実現しやすくなります。
クリティカルシンキングのメリット
クリティカルシンキングを取り入れることによって、主に3つのメリットを得られます。
- 物事の本質を見極められる
- 問題解決や意思決定の質が高まる
- 新たな発想を見つけられる
物事の本質を見極められる
クリティカルシンキングは、前提から思考していくため、答えに近づく過程で余計な部分が削ぎ落されていきます。そのため、最終的な答えが導き出されたときに、本質を見極めることが可能です。
物事の本質がわかるようになれば、手法自体を再検討したり、異なる方法を提案したりするなど、根本から改善を図ることができます。
問題解決や意思決定の質が高まる
物事をそのまま受け入れている状態では、矛盾や漏れに気づかないケースもあります。十分に検討しないまま進行してしまえば、防げたミスやトラブルが起きるかもしれません。
クリティカルシンキングは、多角的に物事を考察し、矛盾や漏れが出ないように深堀りする思考法です。本質的な課題に気づいたり、様々な視点からの考察で誤りを発見したりすることによって、問題解決や意思決定の質が高まります。
新たな発想を見つけられる
クリティカルシンキングに取り組む過程で、新たな発想や視点を見つけられることもあります。例えば、人員が不足しているという主張に対して、そのまま受け入れると「人員を補充しよう」という発想になるでしょう。
実際は、人員が足りないのではなく、人員に対する仕事量や働き方の効率に問題がある可能性もあります。
そこでクリティカルシンキングを行うと、仕事量を適切に調整しよう、システムを導入して効率化を図ろうなど、異なる角度でアプローチできます。様々な発想を比較することによって、より効果的な対策を講じることができるでしょう。
まとめ
クリティカルシンキングは前提から問う思考法であり、本質を見極められたり、問題解決や意思決定の質を高めたり、新たな発想を見つけたりできるメリットがあります。
効果的に実践するためには、前提を疑う、問い続ける、思考の癖を理解するといった姿勢を持つことが重要です。ロジカルシンキングとの違いや4つのステップも参考にして、クリティカルシンキングを実践しましょう。